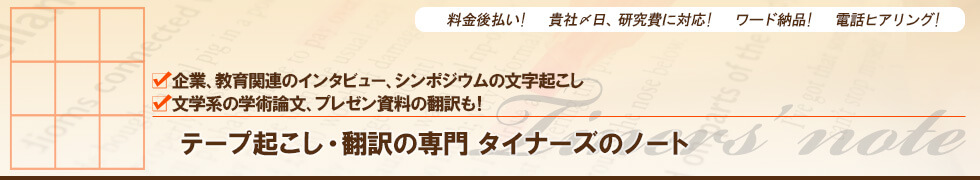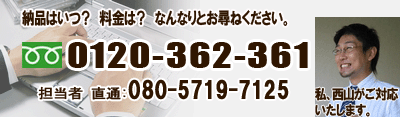データの海で
美咲は深夜のラボで、モニターの光に照らされながら、山のようなインタビュー記録と向き合っていた。修士論文の提出まであと三ヶ月。彼女の研究テーマは「地方都市における高齢者の孤立感とコミュニティの役割」。半年かけて収集した30人分のインタビューデータが、今や彼女の前に立ちはだかる巨大な壁となっていた。
「田中さんは『近所づきあいが希薄になった』と言ってたけど、佐藤さんも似たようなことを…でも、微妙に違う。これをどうコード化すればいいんだろう」
美咲は頭を抱えた。指導教官の山田教授からは「コード化とカテゴリー化をしっかりやりなさい」と言われているが、実際にどうすればいいのか、頭では分かっていても手が進まない。
そんな時、研究室の先輩である拓也が差し入れのコーヒーを持ってやってきた。
「まだやってるの?美咲ちゃん、もう2時だよ」
「拓也先輩…。データが多すぎて、どこから手をつけていいか分からないんです。同じような話でも、微妙に違うし、これをどうやってコードにすればいいのか」
拓也は美咲の隣に座り、画面を覗き込んだ。
「ああ、この段階ね。僕も去年、同じところで悩んだよ。コード化って、データを殺すことじゃないんだ。むしろ、データの中に隠れている物語を見つけることなんだよ」
物語を見つける
翌日、美咲は拓也に教えてもらったサイトを見ていた。「コード化・カテゴリー化で研究素材を整理する」という文字が目に飛び込んでくる。
複数の記事を読みながら、美咲は昨夜の自分の悩みがそっくりそのまま書かれていることに驚いた。「ふむふむ」である。
田中おばあちゃんが「公園で一人でいる時の寂しさ」を語ったのに対し、佐藤おじいちゃんは「自宅で一人でいる時の寂しさ」を語っていた。場所は違うが、根本的な感情は同じ。これをどう扱えばいいのか、サイトには具体的な方法が書かれていた。
美咲は興奮して、すぐに拓也にメッセージを送った。
「先輩!すごいサイト教えてくれてありがとうございます!今から試してみます!」
コードが語り始める時
それから一週間、美咲は毎日深夜までデータと向き合った。しかし、今度は以前のような絶望感はなかった。タイナーズのサイトで学んだ方法を使いながら、一つ一つの発言を丁寧にコード化していく。
「孤立感-物理的距離」「孤立感-心理的距離」「コミュニティ-期待と現実のギャップ」…
コードが増えるにつれて、美咲は不思議な感覚に襲われた。バラバラだった30人の高齢者の声が、少しずつ一つの大きな物語として見えてくるのだ。
そして、ある夜のこと。美咲はコードをカテゴリーごとに並べ替えている時に、はっと気づいた。
「これって…高齢者の方々が求めているのは、単なる『交流』じゃなくて『役割』なんだ」
データの奥に隠されていた真実が、まるで霧が晴れるように見えてきた。彼らが語る孤立感の背景にあるのは、社会から必要とされなくなったという感覚だったのだ。
データから物語へ
美咲の発見は、指導教官の山田教授も驚くほどだった。
「美咲さん、これは素晴らしい分析ですね。単なる孤立感の研究ではなく、高齢者の社会的役割に関する新しい視点を提示している。コード化とカテゴリー化がうまくいった証拠です」
美咲は嬉しかった。しかし、それ以上に、30人の高齢者の方々の声が、きちんと学術的な形で世の中に伝わることに意味を感じていた。
「先生、私、気づいたんです。コード化って、データを数字に変えることじゃないんですね。人の声を、もっと多くの人に届く形に翻訳することなんだ」
山田教授は微笑んだ。
「そうです。研究者の仕事は、一人一人の体験を、社会全体の課題として可視化することです。美咲さんは、それができるようになった」
新たな研究者として
修士論文の発表会当日。美咲は自信を持って研究成果を発表した。聴衆の中には、インタビューに協力してくれた高齢者の方々もいた。
発表後、田中おばあちゃんが美咲に近づいてきた。
「美咲ちゃん、私たちの話が、こんなふうに大きな意味を持つなんて知らなかったよ。ありがとうね」
美咲は涙が出そうになった。データ分析の技術を学ぶことで、人の声により深く寄り添うことができるようになった。それが何より嬉しかった。
夜、美咲は再びサイトを開いた。今度は、自分が学んだことを後輩に伝えるために。コード化とカテゴリー化の技術は、単なる分析手法ではない。それは、人と人をつなぐ架け橋なのだと、美咲は確信していた。
そして、博士課程への進学を決意しながら、彼女は新しい研究テーマについて考え始めていた。今度は「研究手法の学習が研究者のアイデンティティ形成に与える影響」について。
データの海で迷子になった一人の学生が、コード化の技術を通じて、真の研究者として生まれ変わる物語。それもまた、誰かの研究テーマになるかもしれない。
―――
編集後記:
実際に質的研究に携わったことがある方なら、美咲がデータの海で迷子になる気持ちや、コード化の過程で突然「見えてくる」瞬間の感動を、きっと共有していただけるのではないでしょうか。一見すると技術的で無機質に思えるコード化という作業が、実は人の声に最も深く耳を傾ける作業でもある、という逆説的な真実を描きたかったのです。
美咲が最終的に「研究手法の学習が研究者のアイデンティティ形成に与える影響」という新しいテーマに興味を持つという設定は、この物語そのものがメタ的な構造を持っていることを示しています。研究について研究するという入れ子構造の中に、現代の学問の自己言及的な性質を込めました。